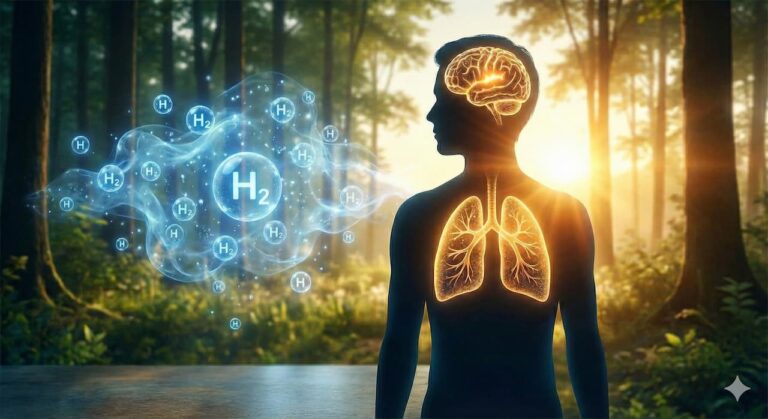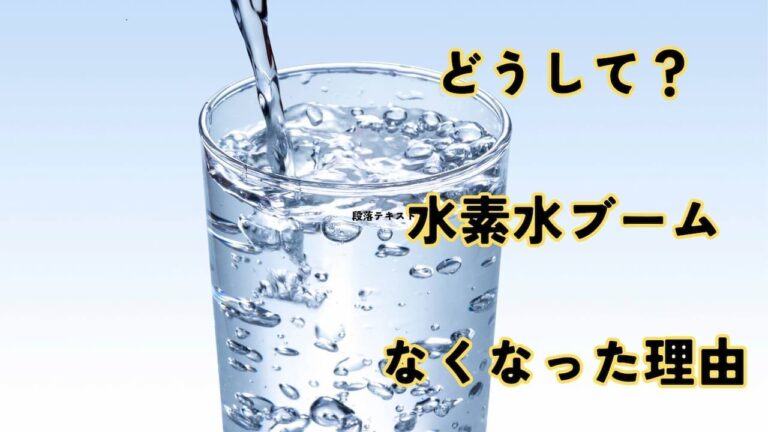水素ガス吸入療法は心停止後症候群に対する療法として、厚生労働省から先進医療Bの承認と取り下げを経て、現在も研究が続けられています。本記事では、水素ガス吸入療法における研究の歩み、最新の研究動向、将来性、そして当社の事例までを詳しく解説していきます。
水素ガス吸入療法の現在までの歩み
水素ガス吸入療法は、基礎研究から臨床試験に至るまで着実に歩みを進めています。まずは水素ガス吸入療法の主要な節目を時系列で解説していきます。
2007年5月:「水素分子に活性酸素を還元する働き」の論文発表
まず水素ガス吸入療法の研究の幕開けとも言えるのが、2007年にOhsawaらによって発表された研究データです。(参照:Nat Med 13 , 688–694 (2007))
この研究では、水素ガスは強力な抗酸化作用を示し、活性酸素を選択的に減少させることが発表されました。つまり、さまざまな病気の原因になる活性酸素を水素ガスが減少させる効果が期待でき、治療用抗酸化物質として有効なことが示唆されたのです。
2016年7月:パイロット研究結果の発表
先進医療承認に向けて行われていたパイロット研究の結果が2016年7月に発表されました。体温管理療法(TTM)と水素ガス吸入療法を18時間実施した結果、心停止蘇生後の5症例のうち、4症例はCPC1と良好な回復をみせました。
パイロット研究の結果概要▼
出典:2016 Volume 80 Issue 8 Pages 1870-1873
CPC(Cerebral Performance Category)とは、心肺蘇生後などの患者の脳機能の状態を評価するためのスコアで、1~5に分類されています。
<CPC>
| スコア | カテゴリ | 概要 |
| 1 | 正常(脳機能良好) | 意識があり、注意力があり、仕事ができ、通常の生活を送れる |
| 2 | 中等度の障害(障害はあるが自立している) | 意識があり、保護された環境でパートタイムの仕事や日常生活の独立した活動(例:服を着る、公共交通機関で移動する、食事の準備をする)を行うのに十分な脳機能がある |
| 3 | 重度の障害(意識はあるが障害があり、介助が必要) | 意識はあるが日常的なサポートは他者に依存している、認知能力は少なくとも限られている |
| 4 | 意識不明(昏睡または植物状態) | 無意識、周囲の状況に気づかない、認知能力がない、環境との言語的または心理的な相互作用がない |
| 5 | 脳死 | 脳死または死亡の基準を満たす |
参照:MSDマニュアル
パイロット研究の結果から、水素ガス吸入療法は心停止蘇生後の転帰が良好なことが示唆されました。
2016年12月:先進医療Bに承認
パイロット研究の結果を受けて、厚生労働省は2016年12月に水素ガス吸入療法を「心停止後症候群(PCAS)」に対して先進医療Bの適用対象とする認定を行いました。
先進医療とは▼
出典:厚生労働省
心停止後症候群とは、心停止から自己心拍が再開した後も、全身の虚血・再灌流障害によって引き起こされる複数の病態の総称です。具体的には以下のような病態が含まれています。
<心停止後症候群の例>
| 主な病態 | 概要 |
| 心停止後脳障害(蘇生後脳症) | ■心停止によって脳への酸素供給が途絶え、脳細胞に損傷が生じた状態
■意識障害、痙攣発作、長期的な脳機能障害などを引き起こす場合がある |
| 心停止後心筋機能不全 | ■心拍が再開しても、虚血と再灌流によって心臓のポンプ機能が低下した状態 |
| 全身虚血再灌流反応 | ■心停止後に全身の臓器に血液と酸素が再供給されることで、炎症を引き起こす物質(サイトカインなど)が放出され、全身的な炎症反応が生じた状態 |
| 心停止に至った病態の継続 | ■心停止の原因となった元の病気(心筋梗塞、不整脈など)が引き続き影響を与え、病態が悪化した状態 |
心停止後症候群への対応を早期に行うことが、救命率やその後の社会復帰率を改善するうえでとても重要です。水素ガス吸入療法が心停止後症候群に対して有効である根拠をさらに確固たるものにし、保険診療への組み込みを目指して、各関連医療施設で本格的に臨床試験が開始されました。
2022年3月:先進医療Bからの取り下げ
心停止後症候群において先進医療Bの認証を受けた水素ガス吸入療法ですが、残念ながら2022年3月に取り下げが決定しました。
この取り下げは、COVID-19パンデミックの影響により臨床試験の被験者登録数(n数)が十分に確保できなかったことが主な理由です。そもそも心停止後症候群の原因である心停止は一刻を争う救命現場で発生するため、同意書の取得や家族との連絡など、倫理的手続きの制限が大きいと言えます。コロナ禍ではさらに面会や接触が厳しく制限されたことが患者登録の困難さに拍車をかけたのです。
研究実施計画書の目標症例数は360例でしたが、結果は73例。そのため、研究実施計画書に定められた中止基準に則って中止が決定しました。
2022年11月:アメリカ心臓協会蘇生シンポジウムで研究発表
心停止後症候群への水素ガス吸入療法は先進医療Bから取り下げられましたが、有効な研究結果は得られています。2022年11月に開催されたアメリカ心臓協会蘇生シンポジウムでは、慶應義塾大学病院を主幹とする研究グループが国内15施設で行った臨床試験結果を発表しました。
心停止を起こした患者に対して「通常の体温管理療法に加えて、2%水素添加酸素を18時間吸入する群」と「対照群」の90日後の経過は以下の通り。
<研究発表の主な概要>
- 後遺症なしの社会復帰率:対照群20%、水素ガス吸入療法群46%
- 生存率:対照群61%、水素ガス吸入療法群85%
心停止を起こした患者に対して水素ガス吸入療法を取り入れたことで、後遺症をのこさず社会復帰ができた患者の割合や生存率が改善したことが公に発表されました。この成果は、心停止後症候群治療における水素ガス吸入療法の臨床的意義を示す重要なエビデンスとして注目され続けています。
水素ガス吸入療法の将来性
続いて、水素ガス吸入療法の将来性について、期待されている研究などについて紹介していきます。
心停止後症候群での研究継続
アメリカ心臓協会蘇生シンポジウムで研究発表があったように、心停止蘇生患者に対する水素ガス吸入療法の安全性と有効性が証明されたため、Phase III 臨床試験に向けた準備が進められています。
| 臨床試験とは?
人間に対して医薬品の投与あるいは医療機器の使用などの介入行為を行い、ある決められた時点から情報を収集するもの。臨床試験は、安全性と有効性を確かめながら段階的に進められ、4つの相(Phase I~Phase Ⅳ)に分類される。 Phase I:最初の段階の臨床試験。 Phase II:2番目の段階の臨床試験。 Phase III:3番目の段階の臨床試験。 Phase Ⅳ:承認・市販後に行われる臨床試験。 |
参照:TR・治験センター
慶応義塾大学の水素ガス治験開発センターでは、販売前の臨床での最終試験であるPhase IIIに向けて、関連会社と協力しながら、水素ガスや水素ガス供給装置の薬事承認に向けた活動を進めていくと表明しています。
他の疾患への応用研究
水素ガス吸入療法は心停止後症候群にとどまらず、がんや神経疾患、代謝性疾患などにも広がりを見せています。以下は水素ガスに関わる主な基礎研究の例です。
<水素ガスに関わる基礎研究の例>
水素には抗酸化作用と抗炎症作用があることから、さまざまな疾患の改善や軽減に効果が期待できるようです。基礎研究段階のテーマですが、研究を重ねることで臨床試験や薬事承認などが期待できるものもあり、水素ガスの可能性は幅広いと言えるでしょう。
日常生活への活用
医療現場での研究が進む一方、水素の抗酸化作用や抗炎症作用に注目し、一般の健康維持や美容、疲労回復などに応用する動きも広がっています。日常で水素ガスを活用できるものには以下のようなものがあります。
<医療以外で活用されている水素ガスの例>
- 水素水
- 水素吸入
- 高濃度水素風呂
- 水素を含む化粧品
これらの製品や使用用途はあくまで補助的な位置づけであり、必ずしも医学的根拠が確立しているとは限りません。発展途上の研究も多く、効果には個人差があります。どのような症状に、どのような条件で効果があるのか、根拠を慎重に見極めながら日常生活に役立てていきましょう。
水素ガス吸入療法の事例
最後に当社に寄せられた水素ガス吸入の事例を一部紹介していきます。
<水素ガス吸入療法の症例と経過>
| 症例 | 年齢/性別 | 吸入条件 | 経過・結果 |
| 慢性COPD | 60代/男性 | 2000ml/分を1年以上、その後4800ml/分に切替え | ■痰の絡みが軽減し、呼吸がより楽になった |
| 卵巣がん(ステージ4) | 50代/女性 | 4200ml/分を毎日5時間 | ■抗がん剤の副作用軽減
■胸水が治癒 ■腫瘍4cmが2cmに縮小 |
| 乾癬 | 60代/男性 | 1200ml/分を約2か月間
+水素風呂を併用 |
■約2か月で皮疹が大幅に改善
■内部・外部両面からのアプローチが奏功 |
| 血流改善 | 記載なし | 水素+酸素同時吸入を30分 | ■暗視野顕微鏡観察で赤血球が連結しないサラサラ血液状態に変化 |
| 網膜浮腫 | 81歳/女性 | 2000ml/分を週2回
悪化後4800ml/分を週2回に切替 |
■悪化したことで手術予約をし、水素ガス吸入量を変更
■吸入量を変更したことで、手術予定日の再検査で浮腫がほぼ消滅し、手術不要になった |
参照:事例集
これらの事例はあくまで個別例であるものの、水素ガス吸入療法が各症状を和らげる効果を期待させる報告でした。詳細が気になる方は、ぜひ当社の事例集をご覧ください。
水素ガス吸入療法の現在と将来性|厚生労働省等の情報を紐解く【まとめ】
水素ガス吸入療法は、厚生労働省によって正式に「先進医療B」として認められた実績を持つ、科学的根拠に基づく医療技術です。その後の取り下げは、研究体制や外的要因によるものであり、水素ガス吸入療法が「無効」と判断されたわけではありません。むしろ、臨床データの蓄積と安全性の検証が進むことで、将来的に再び公的医療制度に組み込まれる可能性があります。
当社は水素吸入器の製造・販売を行っております。機器の無料体験やレンタルも行っておりますので、興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。